徒手療法の世界に身を置いて 第46回
「立ち位置を見直してみよう」
テクニックや検査において上手くいかない先生方に共通して言えるのが、「立ち位置」。立ち位置が悪いと、どうしても無駄な力がかかってしまいます。
2つの基本的な姿勢
安定した姿勢をつくるためには、スタンスが大切です。徒手療法で使用されるスタンスには、スクエア・スタンスとフェンサーズ・スタンスという2つの姿勢があります。簡単に言うと、スクエア・スタンスは患者さんに向かって直角に位置する立ち方で、足は左右に開きます。それに対してフェンサーズ・スタンスはフェンシングのスタイルのように足を前後に開いて立つ姿勢を言います。
姿勢を安定させるためには
運動学の分野では、いくつかの要素が姿勢の安定に不可欠です。その中でも、大切なのが支持基底面の広さと支持基底面の中に自分の重心が入っていること。そして重心の高さです。支持基底面とは、両方の足底の面積とその間にできる面積のことで、これが広ければ広いほど安定します。長方形の長辺を下にした方が、短辺を下にするよりも倒れにくいことで理解できると思います。また、片足立ちでは支持基底面が片方の足底面積だけになり、支持基底面が狭く重心がそこから出ていきやすくなります。最後に重心の高さですが、これは低ければ低いほど安定します。
例えば脊柱のモーション・パルペーション
個人差はありますが、だいたい脊柱の長さは50cmほどです。単純に支持基底面を50cmにすれば、理論上は大丈夫だということになります。しかし脊柱には弯曲があり、圧をかける方向が脊柱に対して直角に押圧するのであれば、支持基底面はそれよりもっと広く取る必要が出てきます。例え支持基底面を広く取ったとしても、患者さんの体型やテーブル(施術台)の高さによって実際的には無理でしょう。こういったケースでは、少しずつ自身の立ち位置を変化させる必要があります。
例えコンタクトができても、自身の身体に負担をかけていれば良い施術にはなりませんし、知らず知らずのうちに施術者の身体を痛めてしまうことになりかねません。また、それらは患者さんの負担にもつながっていきます。
最近、施術するのが辛いとか、検査していると肩や肘が痛いとか感じている先生は、一度ご自身の立ち位置を見直してみてはいかがでしょうか? 身体にかかる負担だけではなく、検査や施術を行いやすくなるかもしれませんよ。
5月開催!Webセミナー徒手療法家のための基礎講座『神経筋骨格障害』
辻本 善光(つじもと・よしみつ)
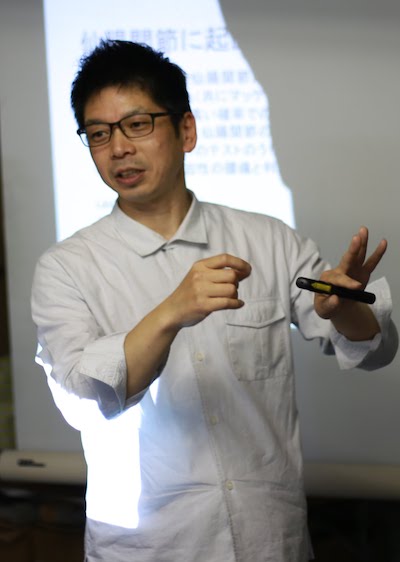
東大阪市にあったインターナショナル・カイロプラクティック・カレッジ(ICC、旧・国際カイロ)に22年間勤め、その間、教務部長、臨床研究室長を務め、解剖学、一般検査、生体力学、四肢、リハビリテーション医学、クリニカル・カンファレンスなど、主に基礎系の教科を担当。
(一社)日本カイロプラクティック徒手医学会(JSCC)の学術大会ではワークショップの講師を、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の設立当初には試験作成委員を務める。ICCブリッジおよびコンバージョン・コースの講師、また個人としてはカイロプラクティックの基礎教育普及のため、基礎検査のワークショップを全国各地で開催するなど、基礎検査のスペシャリストとして定評がある。
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。