徒手療法の世界に身を置いて 第45回
「安全性と危険性」
先月から「頚椎アプローチの安全性を求めて」というWebセミナーをやらせてもらっています。頚椎の事故は重篤な後遺症をもたらすほか、最悪のケースでは死に至らしめることもあり、それゆえにリスク管理が重要になるのは当たり前のことでしょう。
施術方法は施術者によって異なる
徒手療法には様々な手技があります。カイロプラクティックにおけるアジャストメントであれ、モビリゼーションであれ、筋エネルギー・テクニック(MET)であれ、その手技に長けた施術者であれば、患者さんに恩恵をもたらすことができます。これらの手技の違いは、患者さんに与える刺激の量にあります。アジャストメントであれば突発的なスラストという操作を行いますし、モビリゼーションであれば緩やかな反復刺激となり、METでは患者さんの自発的な筋収縮を用います。
刺激の量が危険なのか?
刺激の量だけで考えれば、もちろん突発的な力を用いるスラスト法が、「危険だ」という印象を持たれるかもしれません。その逆に自発的筋収縮を用いるMETは「安全だ」という印象を与えるかもしれません。本当にそうなのでしょうか? 以前、赤ちゃんの施術で死亡事故が起こったという事例がありました。この施術者は、赤ちゃんに突発的な力を用いた施術をしたのでしょうか? そうではないでしょう。突発的な力を用いない施術であっても事故は起こりますし、危険性が少ないというだけで安全性が高いとは言い切れません。
治せる技術は壊せる技術
患者さんを壊そうとする施術者はいないと思います。しかし結果的に、治らない、良くならないということは臨床に携わっている以上、常に付きまとう問題です。同じ施術をしているのに、良くなっていく患者さんと良くならない患者さんがいるとすれば、両者の違いは一体何だったのでしょうか、施術手技が悪かったのでしょうか、もちろん臨床を始めたばかりの若い施術者なら、そういうこともあるかもしれません。しかし何年も臨床に携わっている施術者が、こういった問題を起こすとしたら、手技的な問題ではなく患者さんの状態を把握できていなかったから、というケースが多いように思えます。刺激を加える必要のない部位、または刺激を加えてはいけない部位に刺激を加えたら、良くなるわけがありませんし悪化して当然でしょう。
治せなくても壊さない
これはヒポクラテスの有名な言葉です。一度は耳にされた先生方も多いと思います。しかし前述したように、事故はいつ起きても不思議ありません。例え、刺激が少ない「安全であろう」という手技をしたとしても、「危険性」がないとは言い切れません。安全性と危険性は同じようで同じではないのです。テクニック・セミナーなどでは、基本的に「安全で効果のある手技」が紹介されます。多くの施術者はこのようなセミナーで技術を学び、患者さんに提供しているのでしょう。しかし、施術の「危険性」を最小限にするための一番の方法は、患者さんの状態を把握することでしか除外されないのです。これは手技を行う以前の問題であり、実際に報告されている頚椎事故は、「器質的疾患」を除外できずに施術した結果が圧倒的に多いのです。
知識と検査で「危険性」を最小限に除外し、できる限り「安全性」の高い技術の研鑽によって、患者さんの回復に日々努める必要があるでしょう。これは「人を診る」立場にある施術者の最低限の責任ではないでしょうか。
辻本 善光(つじもと・よしみつ)
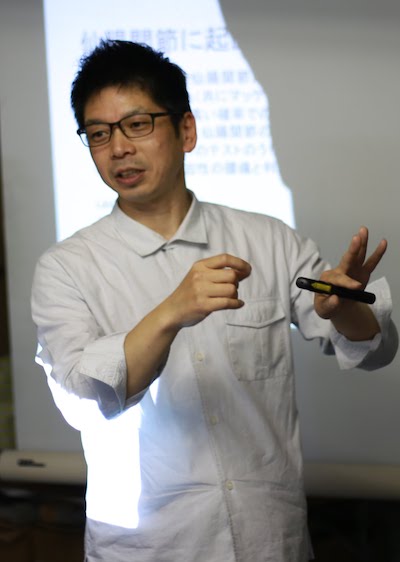
東大阪市にあったインターナショナル・カイロプラクティック・カレッジ(ICC、旧・国際カイロ)に22年間勤め、その間、教務部長、臨床研究室長を務め、解剖学、一般検査、生体力学、四肢、リハビリテーション医学、クリニカル・カンファレンスなど、主に基礎系の教科を担当。
(一社)日本カイロプラクティック徒手医学会(JSCC)の学術大会ではワークショップの講師を、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の設立当初には試験作成委員を務める。ICCブリッジおよびコンバージョン・コースの講師、また個人としてはカイロプラクティックの基礎教育普及のため、基礎検査のワークショップを全国各地で開催するなど、基礎検査のスペシャリストとして定評がある。
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。