徒手療法の世界に身を置いて 第48回
「守破離」
臨床の現場では応用力が試されます。腰痛一つとっても、施術部位や施術法が全く同じではなく、患者さんの状態に合わせて修正されていきます。
守破離
武道など修行の段階で「守破離」というものがあります。「守」は師や流派の教えを忠実に守り、基本の型や技を習得する段階。「破」は師の教えを基本としつつ、他の教えも取り入れたり、独自の工夫を加えたりして、型を応用・発展させる段階。「離」は師の教えや型から完全に離れ、それまでの学びを基に自身の新しい型や技をつくり出していく段階とされています。
臨床の現場での応用力や修正力は「破」
患者さんの状態に合わせての修正力や、体格差からその技術ができない場合の応用力は、まさに「破」と言っても良いでしょう。また、テクニック・セミナーなどでの講師の技術も、自身の経験や患者さんの反応から、少しずつ修正されたものになっていくでしょう。大切なことは、どのような考えで、その技術は何をするために行われるのかということを考えることです。ここを考えなければ、その講師の「破」にあたる2段階目が、受講生にとっては「守」になるため、レベルの高い基本になってしまいます。
知識における守破離
知識の面でも同じで、臨床の現場における応用力や修正力には守破離が必要になります。基本的なことを知らなければ、何をどうすれば良いのかが見えてきません。ちょっと難しい話を聴いて右から左に忘れてしまうのも、「守」が足りないということになるのかもしれません。また、講師が「何を言っているのか全くわからない」のも同じでしょう。基礎知識があるからこそ、話を聴くことができ、その知識を基に技術の修正ができるようになります。しかし、基本の知識を「そんなこと知っています」「とうにわかっています」と、理解したつもりになっている人を多く見かけますし、繰り返し、繰り返しイメージしていないと忘れてしまうこともあるでしょう。
結果が良くない、良くなかった患者さんを考える
良くなっている患者さんは、今の知識と技術で良くなっているので問題ありません。問題なのは、良くなっていかない患者さんをどうするのかが大切なことなんですが、知識や技術はすぐに身につくものではありません。しかし、今ある知識と技術を「守破離」することで、次の来院時に改善していける可能性が出てきます。その過程が修正力や応用力につながり、よりたくさんの患者さんに喜んでもらえる施術家に近づいていくのではないでしょうか?
修正力や応用力は「考える」ことから始まります。「何を言っているのかわからない」「何が言いたいかわからない」「どうすれば上手くなるのか」「この患者さんには今のテクニックは使えない」と考えている先生がいましたら、ぜひ守破離の「守」を見直してみませんか? 考えること、基本的なことからしか解決方法は見つからないと思います。
11月開催!Webセミナー徒手療法家のための基礎講座『機能解剖学-四肢応用編-』
辻本 善光(つじもと・よしみつ)
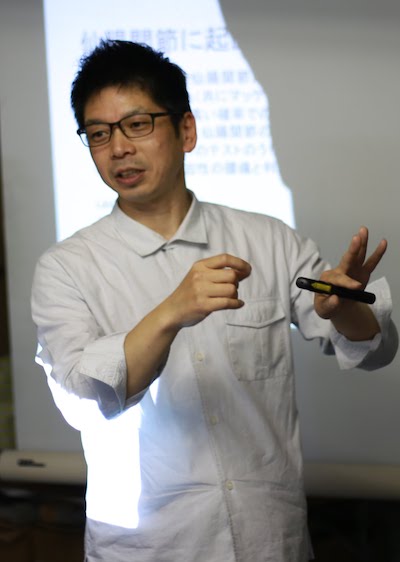
東大阪市にあったインターナショナル・カイロプラクティック・カレッジ(ICC、旧・国際カイロ)に22年間勤め、その間、教務部長、臨床研究室長を務め、解剖学、一般検査、生体力学、四肢、リハビリテーション医学、クリニカル・カンファレンスなど、主に基礎系の教科を担当。
(一社)日本カイロプラクティック徒手医学会(JSCC)の学術大会ではワークショップの講師を、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の設立当初には試験作成委員を務める。ICCブリッジおよびコンバージョン・コースの講師、また個人としてはカイロプラクティックの基礎教育普及のため、基礎検査のワークショップを全国各地で開催するなど、基礎検査のスペシャリストとして定評がある。
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。